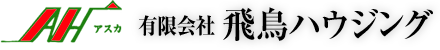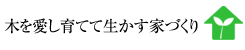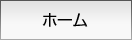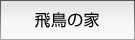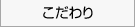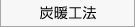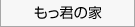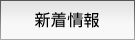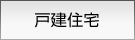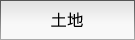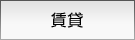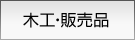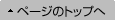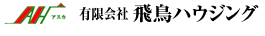すまい給付金#1
-すまい給付金とは?-
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
「すまい給付金」から引用
-給付額は?-
■消費税率8%時の給付額
| 収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額※2 | 給付基礎額 |
|---|---|---|
| 425万円以下 | 6.89万円以下 |
30万円 |
| 425万円超475万円以下 | 6.89万円超8.39万円以下 |
20万円 |
| 475万円超510万円以下 | 8.39万円超9.38万円以下 |
10万円 |
■消費税率10%時の給付額
| 収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額※2 | 給付基礎額 |
|---|---|---|
| 450万円以下 | 7.60万円以下 |
50万円
|
| 450万円超525万円以下 | 7.60万円超9.79万円以下 |
40万円 |
| 525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下 |
30万円 |
| 600万円超675万円以下 | 11.90万円超14.06万円以下 |
20万円 |
| 675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下 |
10万円 |
※2 神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、
所得割額が上表と異なります。詳しくは、すまい給付金のホームページ等をご確認ください。